全国のオススメの学校
-
摂南大学薬学部9学部17学科の文理バランスのとれた総合大学私立大学/大阪
-
和歌山県立医科大学薬学部公立大学/和歌山
-
昭和薬科大学薬学部臨床能力を備えた薬剤師から先端研究に取り組む若手研究者までを育成私立大学/東京
-
長崎国際大学薬学科真の「ホスピタリティ(もてなしの心)」を身につけた心豊かな人材を育成私立大学/長崎
-
京都薬科大学薬学科高度な専門能力と研究能力を合わせ持つ薬剤師を養成する6年制薬学部私立大学/京都
今でこそ世界各国に薬剤師という職業がありますが、かつては医師がその役割を担っていました。日本でも、20年ほど前までは医師が薬剤を調剤するケースは珍しくありませんでした。役割が分かれ、薬剤師が誕生した歴史を紹介します。※文章の一部を変更しました(2018年10月10日)。
薬剤師の始まりは13世紀まで遡る
一説によると、薬剤師制度は、1240年ごろに神聖ローマ帝国のフリードリヒ2世が、主治医の処方した薬による暗殺を恐れて別の者にチェックさせたことが起源だといわれています。のちに彼が定めた「5か条の法律(薬剤師大憲章)」では、医師が薬局をもつことを禁じ、薬の処方と調剤の業務を分離して医師と薬剤師がそれぞれを分担するよう書かれていました。これが世界における「医薬分業」制度の始まりです。
日本における薬剤師の歴史
日本に医薬分業制度が導入されたのは、それから600年以上も後の明治時代初期のことでした。それまでオランダ医学を軸にした医療を行ってきた日本政府は、より進んだ先進医療制度を取り入れようと、ドイツから2人の医師を招きました。当時の日本の医師が診療、調剤、処方のすべてを担っている様子を見た二人は、政府に対して、
「医療は医師単独で行われるものではなく、医師と薬剤師の双方によって成り立つもの。早急に薬剤教育を施するべきだ」
と進言しました。
こうして、日本では「医制」「薬律」を制定し、医師と薬剤師を専門職として切り離すことにしましたが、当時診察料よりも調剤料で生計を立てていた医師たちは猛反発しました。こうした背景から、医薬分業制度はなかなか浸透しませんでしたが、1997年に状況が変わります。当時の厚生省が全国37のモデル国立病院に完全分業(院外処方箋受取率70%以上)を指示したことをきっかけに、各地で取り組みが急速に進み、2015年には全国の医薬分業率がようやく70%を超えました。
それまで薬剤師は主に処方箋に応じた調剤を行っていましたが、完全分業が進むにつれて調剤のほかに患者さんへの服薬指導なども行うようになりました。医師とは異なる立場で、専門的なアドバイスができるようになったのです。
薬剤師のあり方
医師は病気や症状の原因、それに対する効果的な治療法を熟知しているので、薬の知識をもっています。例えば複数の病気や症状をもつ患者に、それぞれ効果的な薬を処方することはできます。
しかし、それらが互いに反応し合って患者の身体に及ぼす影響を想定できるのは、薬の専門家である薬剤師です。薬の効果や投与量のチェックをし、これまでその人が処方されてきた薬の記録をもとにした健康面の確認など、患者の安全を守っているのです。
医療そのもののや歳を重ねてライフスタイルが変化するごとに、薬を服用するシーンや薬そのものの種類は変わってきます。効果や飲み合わせはもちろん、生活環境や体質によって、薬が身体に与える影響は人それぞれ異なるはずです。医薬分業制度が進み、医師と薬剤師双方の専門家の目を通すことで、患者さんは今まで以上に安心して健康的な暮らしを送ることができるようになるのです。
薬剤師になるには?
薬剤師の仕事について調べよう!
薬剤師の仕事についてもっと詳しく調べてみよう!
薬剤師の先輩・内定者に聞いてみよう

薬学部 卒

薬学部 臨床薬学科

健康科学部医療薬学科
薬剤師を育てる先生に聞いてみよう

薬学部薬学科

薬学部
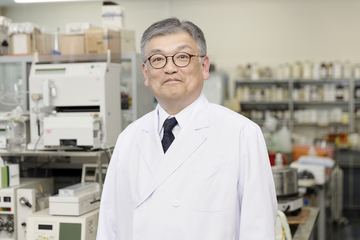
薬学部薬学科
薬剤師を目指す学生に聞いてみよう

薬学部 薬学科

薬学部 薬学科

薬学部医療薬学科
関連する仕事・資格・学問もチェックしよう
関連する記事
-
 薬剤師の仕事内容って?必要な資格から勤務場所、やりがいまで徹底解剖!
薬剤師の仕事内容って?必要な資格から勤務場所、やりがいまで徹底解剖!薬剤師というと、病院・薬局などで薬を調剤したり、ドラッグストアなどで薬の飲み方の説明をしてくれたりする人、というイメージが強いよね。 薬剤師の仕事には、そのほかにも、薬の研究開発や情報提供、流通段階での品質管理、行政での業務など、さまざまな仕事内容があるって知っていた? 勤務場所も、病院、調剤薬局、 …
-
 医薬品に関わる仕事とは? 医療機関、薬局、製薬メーカー、研究機関、場所別に仕事内容を解説!
医薬品に関わる仕事とは? 医療機関、薬局、製薬メーカー、研究機関、場所別に仕事内容を解説!医薬品に関連する仕事というとまず薬剤師が思い浮かぶが、それ以外にも、医薬品を作るために必要な仕事、販売するために必要な仕事は多数ある。 ほとんどの仕事で高い専門性を求められるのが医薬品業界の特徴で、だからこそやりがいも十分。 医薬品を通して人々の健康に貢献したいという高校生は要チェックだ。 医薬品開 …
-
 薬局・病院から食品・化粧品業界まで! 薬学部卒業生のお仕事
薬局・病院から食品・化粧品業界まで! 薬学部卒業生のお仕事大学の薬学部は、「薬剤師になるために学ぶところ」というイメージが強い。6年制の薬学部を卒業した後、薬剤師国家試験に合格して国家資格を取得すれば、保険薬局や病院などで「薬剤師」として働くことができる。 実際、薬学部の卒業生の主な進路は、保険薬局・ドラッグストア・病院が大半。 しかし、実は薬剤師 …
-
 薬学部の6年制と4年制では何が違うの?学ぶこと、資格、就職先など徹底解説!
薬学部の6年制と4年制では何が違うの?学ぶこと、資格、就職先など徹底解説!病院、薬局での調剤や服薬指導、医薬品の管理に、製薬会社での新薬の研究、開発など、社会に必要不可欠な仕事を担う薬学のスペシャリスト。 こうした人材の輩出を使命とするのが薬学部だ。 「人々の健康のために役に立ちたい」「医療の発展に貢献したい」と薬剤師や研究者を志望する高校生も多いだろう。 少し調べたこと …


